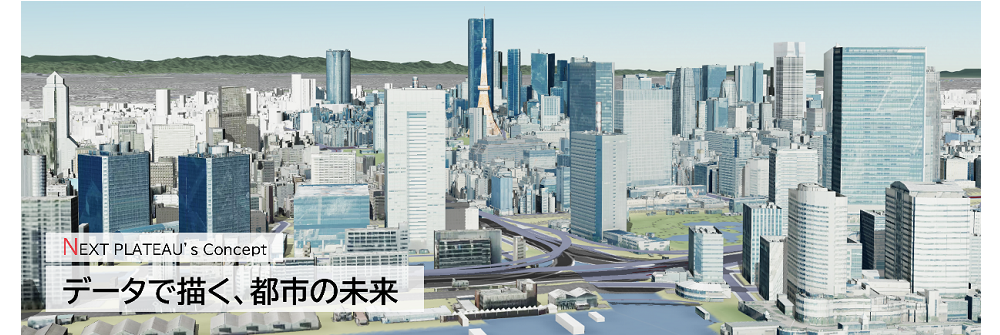コラム
第27回
「デジタルツインが拓く未来」
未来の都市を構築するデジタルツイン技術
前回のコラムでは、「同一性」という概念から、建設分類体系やBIMについて考察しました。未来の建物は、AI(人工知能)によって自律的に改修や増築を行い、都市が自らその姿を変え続ける世界を想像しましたが、その中核となる技術の一つが、「デジタルツイン」といわれるものです。
環境性能を最大化する建物管理
建設業界は今、大きな転換期を迎えています。2030年のカーボンマイナス46%、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、建築物の環境性能はこれまで以上に重要視されています。2025年4月に全面施行される改正建築物省エネ法により、LCA(ライフサイクルアセスメント)やLCCO2(ライフサイクルCO2)といった環境評価要素への関心も高まっています。
このような状況下で、建設業界の救世主として期待されているのが「デジタルツイン」です。設計・施工から維持管理に至るまで、建物のライフサイクル全体にわたってこのデジタルツインの技術を活用することで、環境性能を最大化できる可能性を秘めています。
デジタルツインとは?
デジタルツインとは、現実世界の建築物を仮想空間上に忠実に再現する技術です。実物と同じ形状、構造、材質を持つ3Dモデルを作成し、センサーやIoTデバイスから収集したデータと連携させることで、建物の状態をリアルタイムに把握・分析することができます。
近年、建設業界で普及が進むBIMは、デジタルツインの基礎となる技術と言えるでしょう。BIMは、建物の設計、施工、維持管理の各段階で3Dモデルを活用することで、情報共有や業務効率化を促進する手法です。デジタルツインは、このBIMモデルに現実世界のデータを反映させることで、より高度なシミュレーションや分析を可能にします。
こうした中、国土交通省は、建築BIM推進会議という有識者会議を立ち上げ、BIMの普及やその活用について、議論を行っています。加えて、デジタルツインの計画として、Project PLATEAU(プラトー)という施策も始まっています。
デジタルツインでなにができるのか
デジタルツインは、設計・施工から維持管理に至るまで、建物のライフサイクル全体にわたって活用することで、建設業界のさまざまな工程でその生産性を最大化できると言われています。
例えば、設計段階では、デジタルツイン上で日照や風通しをシミュレーションすることで、自然エネルギーを最大限に活用した設計が可能になります。建物の向きや窓の配置を工夫することで、照明や空調に頼らずとも快適な室内環境を実現できるようになるでしょう。さらに、建材の種類や断熱材の厚さを変更しながらシミュレーションすることで、建物のLCCO2排出量を最小限に抑えることも可能です。
施工段階においても、デジタルツインは力を発揮します。デジタルツイン上で工程管理や進捗状況をリアルタイムに把握することで、資材の無駄な使用や工期の遅延を防ぎ、これが環境負荷を低減することに繋がります。また、建設機械の稼働状況を監視することで、燃料消費量を削減し、CO2排出量を抑えることも期待できます。
環境性能最大化への活用
しかし、デジタルツインの真価が発揮されるのは、建物の維持管理段階です。建物に設置されたセンサーから、エネルギー消費量やCO2排出量などのデータを収集し、デジタルツインに反映することで、建物の状態をリアルタイムに把握できます。AIによる分析と組み合わせることで、設備の故障を予測したり、最適な運転方法を提案したりすることも可能になります。
加えて、空調システムの稼働状況を分析し、室温や外気温に応じて自動的に運転を調整することで、大幅な省エネを実現できるでしょう。

デジタルツインと建設分類体系
さらに、デジタルツインに建設分類体系を導入することで、環境性能の評価・管理はより高度なものになります。建設分類体系とは、建物の構成要素を階層的に分類した体系のことです。この体系に基づいてデジタルツインを構築することで、建物の各部位の環境負荷を詳細に分析できるようになります。例えば、窓や壁、屋根などの断熱性能を個別に評価することで、より効果的な改修計画を立てることができるでしょう。
また、建設分類体系は設計・施工・維持管理の各段階で共通言語として機能するため、デジタルツイン上で情報を一元管理することで、ライフサイクル全体での情報共有がスムーズになります。関係者間で情報が共有されれば、環境負荷低減に向けた継続的な取り組みを促進できるはずです。

建設分類体系についての詳細は、(公社)日本建築積算協会が発行する「BIM概算ガイドブックⅠ」をご覧ください。
環境性能に優れた建物を創造する
「ラプラスの悪魔」
AIが未来の都市を予測し、BIMがその都市を構築する技術だとすれば、それらを統合したデジタルツインは、まさに未来を予見する「ラプラスの悪魔」と言えるかもしれません。膨大なデータと高度なアルゴリズムによって、建物の将来の状態を予測し、環境負荷を最小限に抑える最適な運用を実現する。デジタルツインは、そんな未来を予感させる技術です。
第21回のコラムでご紹介した「ラプラスの悪魔」は、あらゆる事象の因果関係を完全に把握することで未来を予測できる存在でした。デジタルツインは、まさに建物の「ラプラスの悪魔」として、環境性能を最大限に引き出すための道筋を示してくれるのです。
建設DX展のお知らせ
今年も12月11日~13日の日程で、東京ビッグサイトで建設DX展が開催されます。
協栄産業ブースでは、デジタルツインと建設分類体系を組み合わせた最新の技術やサービスを、昨年よりもブースを拡大して展示する予定です。建物の環境性能を向上させるための具体的なソリューションを、ぜひ建設DX展会場で体感してください。
皆様のお越しをお待ちしております!